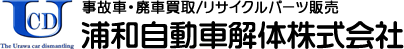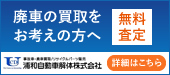スリップサインの確認方法と注意点

タイヤは見た目以上に重要なパーツです。摩耗が進むと雨の日のスリップやブレーキの効きにも影響し、事故のリスクが高まります。そんな危険を知らせるのが「スリップサイン」。タイヤの溝が1.6mm以下になると現れ、交換の目安となる印です。
本記事では、スリップサインの意味や確認方法、見逃した場合のリスク、日常点検のポイントなどを詳しく解説します。
スリップサインは“交換の合図”!目視で確認する方法とその意味
タイヤのスリップサインは、安全な走行を続けるうえで重要なチェックポイントです。見方が分かれば誰でも確認でき、事故や違反の予防につながります。ここでは、スリップサインの意味と確認方法について紹介します。
スリップサインとは?
スリップサインは、タイヤの溝の底にある小さな突起で、摩耗具合を確認するための目印です。タイヤの側面にある小さな三角マーク(△)がスリップサインの位置を示す目印です。タイヤメーカーによって異なりますが、タイヤの側面に4~9カ所あります。タイヤの溝がすり減って、深さが1.6mmになるとこの突起がタイヤと道路が接している面(トレッド面)と同じ高さになり、目視でも分かるようになります。タイヤの縦溝が途切れなく一周していない状態は「限界」のサインでもあり、タイヤ交換が必要なタイミングです。
スリップサインは、安全運転に欠かせない重要な指標の一つ。溝が浅くなると雨天時の排水性が低下し、スリップやブレーキ性能の低下につながります。事故リスクを減らすためにも、日常的なチェックを習慣にしましょう。
また、スリップサインは車検にも影響します。1カ所でもスリップサインが露出していると車検には通りません。走行距離だけでなく、実際にタイヤの状態を目で確認することが、安全性と整備の両面で欠かせないポイントです。
スリップサインのチェック方法
スリップサインを確認するには、△マークの延長線上にあるトレッド面にある縦溝をよく見てみましょう。小さな橋のような突起がスリップサインです。
このスリップサインは、通常1本のタイヤに4〜9か所設けられています。そのため、1か所だけ見て安心せず、タイヤ全体を一周しながら複数の位置を確認するようにしましょう。どれか1つでも突起がトレッド面と同じ高さになっていれば、そのタイヤは寿命を迎えています。
確認作業は、明るい場所で行うのがポイントです。手でタイヤを少しずつ回すか、棒などで角度を調整すると、スリップサインの位置が見つけやすくなります。運転前や給油時、洗車のついでなど、習慣的にチェックすることで見落としを防ぎ、安全性を高められます。
スリップサインの位置を確認しやすくする方法
スリップサインは小さな突起なので、確認する際は見やすい環境を整えることが大切です。まず、暗い場所では溝の奥が見えにくくなるため、スマホなどのライトを使って照らしましょう。また、スリップサインがタイヤの下側にあると地面に隠れてしまい、見づらくなります。そうした場合は、車を少し前後に動かし、タイヤの位置をずらしながらチェックすると確認しやすいでしょう。
さらに、より正確に状態を把握したい場合は、タイヤの溝の深さを測る専用のゲージを使うのも有効です。深さが1.6mm以下であれば、スリップサインが露出している状態と同じと言えます。
カー用品店では、こうした簡易ゲージを無料で配布している店舗があるほか、スマートフォンで測定できるアプリ型ツールも登場しています。ツールを活用すれば、短時間で手軽に点検できるでしょう。
スタッドレスタイヤは「プラットホーム」に注意
冬用タイヤとしての性能を維持するにも、スタッドレスタイヤの摩耗状態を正しく確認することが大切です。目安になるのは「プラットホーム」と呼ばれる突起です。これはタイヤの溝が新品時の半分程度(約5mm)まで減ったときに現れ、雪道や凍結路面でのグリップ力が大きく低下しているサインとして機能します。
プラットホームの位置は、タイヤ側面にある矢印(↑)マークを目印に探せます。その延長線上の溝の中に、四角い突起があり、1本のタイヤに通常4カ所設けられています。1か所だけでなく、全体を確認しましょう。
簡易的に確認したいときは、100円玉をタイヤの溝に差し込み、「1」の数字が見えるかをチェックしてみましょう。「1」は縁から約5mmの位置にあるため、見えている場合は溝が5mm未満になっている可能性があります。
なお、スタッドレスタイヤには通常の「スリップサイン」も設けられています。これは溝の深さが1.6mm未満で現れるもので、タイヤとしての使用限界を示す指標です。一方、プラットホームはあくまで冬用タイヤとしての性能限界を示すものです。両方の違いを理解し、適切なタイミングで交換しましょう。
また、プラットホームが出ていなくても、ゴムの硬化によって性能が落ちている場合があります。使用年数が長い場合や保管状態が悪い場合は、摩耗以外にも注意してタイヤをチェックしましょう。
スリップサインが出たタイヤで走るとどうなる?
スリップサインの露出は、単なる摩耗ではなく、事故や違反のリスクが高まっている状態です。放置して走行を続けると、さまざまなトラブルを招く可能性があります。ここでは、実際に起こりうる走行中のリスクと法律上の影響について紹介します。
走行中に起きるトラブル
スリップサインが見えるほど摩耗したタイヤを使い続けると、走行中に重大なトラブルを引き起こす可能性があります。代表的なのが、雨天時に起きやすい「ハイドロプレーニング現象」です。これはタイヤが路面の水をうまく排水できず、水の上を滑るような状態になることで、ハンドル操作やブレーキが効かなくなる現象です。スピードを控えていても発生することがあり、一般道でも十分に危険です。
さらに、摩耗したタイヤでは制動距離が延びやすくなります。つまり、ブレーキを踏んでから停止するまでの距離が長くなり、とっさの場面で車が止まらないといった状況になります。特に濡れた路面や下り坂では、停止距離のズレが命取りになります。
また、タイヤが長期間使用されるとゴムが硬化し、ひび割れや劣化が進みます。こうしたタイヤは、走行中に突然破裂(バースト)するリスクが高く、車の制御を失う原因にもなります。スリップサインは、こうしたタイヤの限界サインでもあるため、見逃さずに早めの交換を心がけましょう。
法令違反になる
スリップサインが露出しているタイヤで公道を走行することは、法律違反に該当します。道路運送車両法施行規則では、タイヤの溝の深さが1.6mm未満での走行を禁止しており、スリップサインが見えている状態はこの基準を下回っていると判断されるためです。
この状態で走行を続けた場合、道路交通法違反として処理され、普通車であれば違反点数2点に加え、9,000円の反則金が科されます。さらに、もし事故を起こした場合、整備不良と判断され、過失が重くなる可能性があります。保険の補償額が減るだけでなく、内容によっては適用外になることもあるため、事前の確認と対策が重要です。
また、車検でもタイヤの溝の深さはチェック項目の一つです。たとえ1本だけでもスリップサインが出ていれば、その時点で不合格となります。摩耗は気付きにくいため、普段から定期的にタイヤの状態を確認し、早めの交換を心がけましょう。結果的に、不要な出費やトラブルを避ける近道にもなります。
スリップサインを見逃さない!日常点検のすすめ
スリップサインは、事故や違反を防ぐための重要なチェックポイントです。安全な走行を続けるには、日常的な点検を通じてタイヤの摩耗を早めに把握することが欠かせません。ここでは、自分で行う基本的な点検項目と、専門店の活用について紹介します。
日常点検のチェックポイント
安全に走行を続けるには、日常的なタイヤ点検が欠かせません。走行前や給油、洗車のタイミングなどを活用して、定期的に確認する習慣をつけましょう。
まず、スリップサインが出ていないかを目視でチェックします。タイヤ側面の三角マーク(△)を目印に、その延長線上の溝にある突起を確認します。突起がトレッド面と同じ高さになっていれば、そのタイヤは使用限界です。
また、タイヤの摩耗状態もチェックポイント。片側だけ極端にすり減っている場合は、空気圧の調整不良や車両のアライメントに問題があるかもしれません。表面に傷やひび割れがないか、異物が刺さっていないかもあわせて確認してください。
空気圧のチェックは月1回が目安です。熱いと空気が膨張するためタイヤが冷えた状態で測定し、車両の指定値と比較して調整します。空気圧は見た目では判断しづらく、走行性能や寿命にも影響するため、測定器を使って正確に確認することが大切です。
日常点検に必要な道具は、空気圧計などの簡単なものだけです。短時間の確認でも、タイヤのトラブルを防ぎ、結果として修理費や事故リスクを減らすことにつながります。
■日常点検のチェック項目
・スリップサインが露出していないか(三角マークの延長線上を確認)
・偏摩耗がないか(片側だけが極端に減っていないか)
・傷やひび割れ、異物が刺さっているなどがないか
・空気圧は冷えた状態で月1回確認、空気圧を補充しているか
専門店での点検もおすすめ
日常点検では分からない異常や調整が必要な項目もあるため、気になる変化があれば早めに専門店へ相談してください。
専用機器を使って点検してくれるため、目視だけでは分かりにくい溝の深さやゴムの硬さ、摩耗、劣化も数値で把握できます。
また、ホイールの角度がずれていると、片側のタイヤだけが早くすり減る「偏摩耗」が起こります。この状態を防ぐのが「アライメント調整」です。これは、タイヤが正しい角度で地面に接するよう、ホイールの取付角度を調整する作業のこと。アライメントがずれたまま走行を続けると、摩耗が早まるだけでなく、ハンドル操作にも影響が出るため、早めに調整しておきたい項目でもあります。
さらに、走行距離が増えたあとは、タイヤの前後左右の位置を入れ替える「ローテーション」を行うことで、摩耗を均等に保てます。4本のタイヤをバランスよく使い切ることができるため、タイヤ交換までの期間を延ばせるのがメリットです。
| 点検項目 | 内容・目的 |
|---|---|
| 溝・硬さの測定 | 自動測定機器で残り溝やゴムの硬さを確認。精度が高く、短時間で完了 |
| 偏摩耗のチェック | プロが細かく状態を確認し、トラブルの芽を早期に発見 |
| アライメント調整 | 車体の角度を調整し、まっすぐ走るようにする。偏摩耗の防止に効果的 |
| ローテーション | タイヤの位置を入れ替えて摩耗を均一化し、寿命を延ばす |
スリップサインが出る前に、買取査定も一つの手
タイヤにスリップサインが出た状態では、査定価格が下がったり、そもそも買取の対象外になったりすることがあります。ここでは、車両の買取とタイヤの状態の関係性について解説します。
パーツやタイヤは中古でも価値がある
使わなくなったタイヤでも、状態によっては中古市場で買い取ってもらえることがあります。とくに、溝が深く残っていて使用年数が浅いものは、比較的高く評価される傾向があります。スタッドレスタイヤは冬前に需要が高まるため、その時期に売却すれば査定額が上がる可能性もあるでしょう。
査定で重視されるのは、タイヤが4本セットでそろっていること、溝の深さが5mm以上あること、ひび割れや偏った摩耗がないことです。さらに、同じ銘柄・同じ製造時期で統一されていれば、買取側の評価も上がりやすくなります。有名ブランドや日本製のタイヤも、流通性の高さからプラス査定されやすいです。
一方で、製造から年数が経ちすぎていたり、摩耗が進んでいたりするタイヤは、査定対象にならない場合もあります。安価な輸入タイヤも同様で、たとえ外観に問題がなくても、ゴムが劣化していれば買い取りが断られるケースもあります。
処分を考えているタイヤがあるなら、早めに査定に出してみましょう。
廃車・パーツ買取で賢く処分
車の乗り換えや使用しなくなった車は、廃車買取業者に依頼して処分できます。業者によっては車両の引き取り費用がかからないケースもあり、処分にかかるコストを抑えることも可能です。
タイヤやホイール、カーナビ、オーディオなどのパーツもまとめて査定してもらえば、手続きの手間を減らせます。とくにホイール付きのタイヤは、ホイールの素材やメーカーによって評価が変わるため、アルミ製や純正品は高値がつくこともあるでしょう。
車内のナビやオーディオ機器も需要があり、年式が新しいものやメーカーオプション品は、査定額に反映されやすい傾向です。
査定に出す前には、タイヤやパーツの汚れを落とす、付属品や説明書をそろえておくといった準備をしておくと、評価が上がる可能性があります。状態が分かる写真をあらかじめ送っておけば、やり取りもスムーズに進みます。
処分を迷っている段階でも、一度専門業者に相談することで、価値のある部品があるか確かめられるでしょう。タイヤや各種パーツは使用し続けると劣化も進んでしまうため、処分を決めたら早めに査定に出すのがおすすめです。
安全・快適な走行のため、スリップサインを見逃さない
タイヤのスリップサインは、使用限界に達したことを示す重要な目安です。この状態で使い続けると、ブレーキが効きにくくなったり、雨の日に滑りやすくなったりするため、事故のリスクが高まります。タイヤの溝だけでなく、年数やゴムの状態にも注意しながら点検を続けましょう。
不安な点があれば、早めに交換や専門店での確認を検討してください。状態の良いタイヤやホイールであれば、処分前に査定に出すことで、買取対象になることもあります。
浦和自動車解体では、不要になったタイヤやホイールの買取に対応しています。製品の状態やメーカーによっては対象外となる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
お見積もりはお気軽にお問い合わせください!
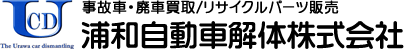
〒338-0824
埼玉県さいたま市桜区上大久保93
TEL 048-854-9923 / FAX 048-855-7848
R京浜東北線 北浦和駅西口より(埼玉大学行き)バス乗車約15分
JR埼京線 南与野駅西口より(埼玉大学行き)バス乗車約10分
「埼玉大学」バス停下車 徒歩約3分