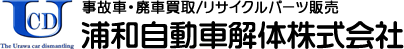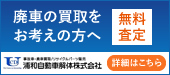タイヤ空気圧の正しい管理と調整方法とは

タイヤの空気圧は、走行性能や燃費、安全性に関わる重要な要素です。目視では判断しづらく、わずかな変化が走りに影響を及ぼします。
空気圧が不足すれば転がり抵抗が増し、燃費の低下や偏摩耗のリスクも高まります。逆に空気を入れすぎると、乗り心地の悪化やグリップ性能の低下を招くおそれもあるでしょう。
本記事では、車両に設定された指定空気圧の確認方法や、サイズ変更時の再設定、一覧表の活用法、点検の基本などについて解説します。日常的な管理に役立つポイントを分かりやすくまとめました。
まず確認すべきは「指定空気圧」
タイヤの空気圧を調整するときは、最初に「指定空気圧」を知ることが基本です。車両ごとの条件に合わせた空気圧の確認方法や注意点を見ていきましょう。
指定空気圧の確認方法
空気圧の調整をする前に確認したいのが、車両メーカーが推奨する「指定空気圧」です。
これは車種やグレードに応じて定められており、もっとも参考にすべき基準値となります。確認方法としては、運転席のドア開口部に貼られているラベルや、車両の取扱説明書を見るのが一般的です。
ラベルには、前輪・後輪ごとの空気圧や、積載状況に応じた調整値が記載されています。同じ車種でもグレードや装備の違いで適正値が異なることがあるため、自分の車の仕様に合った数値かどうかを確認しておくことが大切です。
また、空気圧は走行条件によっても変わります。重い荷物を載せることが多い場合や、複数人で長距離を走るようなケースでは、標準よりも高めの空気圧が指定されているため、ラベルを確認するときは見落とさないよう注意しましょう。
加えて、ラベルや説明書の数値は「冷間時の測定」を前提としています。走行直後や炎天下での測定では、内部の空気が膨張して実際より高い数値が出ることもあるため、確認はなるべく朝方や長時間走行前に行ってください。ガソリンスタンドやカー用品店などで無料の空気圧チェックサービスを活用するのも、手軽な方法です。
サイズ変更時には再設定を
タイヤのサイズを変更した場合や、エクストラロード(XL)規格など荷重性能の高いタイヤへ交換した場合は、空気圧の再設定が必要です。純正の空気圧のままでは、新しいタイヤの特性に合わず、偏摩耗や操縦安定性の低下を招くおそれがあります。特にインチアップによって扁平率が下がると、接地面積や乗り心地に変化が生じるため、適正な空気圧に調整しましょう。
空気圧の設定は、タイヤメーカーが公表している荷重と空気圧の対応表を参考にしたり、販売店や整備工場に相談したりして判断するのが一般的です。高速走行が多い方や長距離を頻繁に運転する方は、特に空気圧管理が快適性や安全性に関わるため注意が必要です。
サイズ変更後は、その都度適正値を見直し、必要に応じて専門店で点検を受けましょう。空気圧はふだん見落とされがちですが、安定した走行や燃費の維持にもつながる大切な項目です。
空気圧の一覧表を使うメリット
タイヤの空気圧を調整するときは、空気圧一覧表を使って数値を確認するのが確実です。空気圧とロードインデックスの対応を見れば、車両の重さや用途に合った設定がしやすくなります。
一覧表のメリット
空気圧一覧表を使うと、自分の車に合った適切な数値がすぐに分かります。特に、タイヤのサイズを変えて、違うグレードのタイヤを使うときに、標準値と比較しながら考えられるので便利です。この一覧には、空気圧ごとにどれくらいの荷重に耐えられるかが書かれていて、「この空気圧なら、この重さまでOK」という関係性がひと目で分かります。
それを参考にすれば、車の重さや乗る人数に合わせて空気圧をどう調整するか判断しやすくなるでしょう。
また、多くの表は以下のようにタイヤの規格ごとに分かれています。
・STD(標準規格)
・XL(エクストラロード規格)
・LT(商用車用の規格)
タイヤ交換の前後で規格が変わる場合でも、一覧表を見れば迷わず適した空気圧を調べられるのがメリットです。
「ロードインデックス(LI)」を軸に確認
タイヤの空気圧を確認するときに、一緒に見ておきたいのがロードインデックス(LI)です。LIは、タイヤ1本が支えられる荷重の目安を表す数値で、数字が大きくなるほど、より重い荷重に対応できます。
一覧表には、各LIに対してどれくらいの空気圧が必要かがまとめられていて、「このタイヤにこの空気圧を入れれば、これくらいの重さまで耐えられる」といった対応関係が分かります。この情報があれば、タイヤを選ぶときに、オーバースペックのものを選んでしまったり、逆に足りなかったりするリスクを減らすことができます。
また、車に乗る人数や荷物が多いとき、あるいは走る環境に負荷がかかる場合などでも、LIと空気圧の組み合わせを見れば、より正確な設定ができるようになります。
XLタイヤやLTタイヤも対応
エクストラロード(XL)タイヤは、内部の構造が強化されていて、標準規格のタイヤよりも高めの空気圧が必要です。同じサイズでも、XLタイヤの場合は空気圧を一割から二割ほど多めに設定することで、タイヤ本来の性能を発揮できます。
ライトトラック(LT)規格のタイヤは、商用車向けに作られており、さらに高い空気圧が設定されているのが一般的です。バンや軽トラックなど、重い荷物を積む前提の車では、LT規格のタイヤとそれに見合った空気圧にしましょう。
このように、タイヤの規格が違えば適切な空気圧も変わってきます。一覧表を参考にしながら空気圧を調整すれば、安全性や耐久性を保ちながら使うことができます。
空気圧が低くても高くても良くない
タイヤの空気圧は、適正値より下がっても上がっても、さまざまな不具合につながります。ここでは、低すぎる・高すぎる空気圧が車に与える影響を紹介します。
空気圧が低い場合
空気圧が不足したまま走行を続けると、燃費の悪化やタイヤの偏摩耗といった問題が起こりやすくなります。見た目では気付きにくいため、日頃の点検が欠かせません。
燃費が悪化しやすくなる
タイヤの空気圧が低いと、たわみが大きくなり、転がるときの抵抗が増加します。その結果、エンジンにかかる負荷が大きくなり、燃料の消費量も多くなる傾向です。街乗りのような短距離の走行でも、燃費が数パーセント低下する場合があります。長距離の運転が多い方にとっては、年間の燃料代に差が出る原因にもなるでしょう。省エネ運転を意識している方にとっては、注意しておきたいポイントです。
また、アイドリングストップ機能やハイブリッドシステムなどが搭載されている車でも、空気圧が適正でなければ十分な効果は期待できません。
「給油の頻度が増えたように感じる」といった場合には、タイヤの空気圧を確認してみることをおすすめします。
タイヤが偏摩耗しやすい
タイヤの空気圧が不足していると、接地面の外側に大きな負担がかかります。この状態が続くと、トレッドの外側だけが極端にすり減る「偏摩耗」が起きやすくなります。偏摩耗が進んだタイヤは、見た目の溝が残っていてもグリップ力が低下し、制動距離が延びてしまうでしょう。また、ハンドリングに違和感が出る可能性もあり、注意が必要です。
さらに、偏摩耗によってタイヤのバランスが崩れると、走行中にハンドルが左右どちらかに引っ張られるように感じることがあります。このままの状態で使い続けると、サスペンションやステアリング機構に負荷がかかるでしょう。結果として、別の修理が必要になるかもしれません。
偏摩耗が進行すると、タイヤの寿命が縮まるだけでなく、走行時の安全性にも支障をきたす恐れがあります。
空気圧が高い場合
空気の入れすぎもまた問題です。グリップ性能の低下や乗り心地の悪化など、目に見えない部分で影響が広がるため注意が必要です。
グリップ力の低下に注意
空気圧が高すぎると、タイヤの中心部だけが膨らみ、路面にしっかり接地しなくなります。その結果、接地面積が減少し、雨天時や滑りやすい路面ではグリップ力が不足するおそれがあります。特にカーブの多い道路では、タイヤが十分に路面をつかめず、曲がりにくさやふらつきを感じることがあるでしょう。さらに、空気を過度に入れすぎた場合は接地面積が狭まり、車種や路面の状況によってはABSやトラクションコントロールが作動しやすくなります。タイヤの性能を引き出すには、設計通りの接地面積を保つことが重要です。
乗り心地の悪化
過剰な空気圧によりタイヤが硬くなると、路面の凹凸をそのまま車内に伝えてしまいます。結果として、走行中に振動や突き上げが増え、乗り心地が悪く感じられるでしょう。
短距離の移動であれば我慢できる範囲かもしれませんが、長時間の運転では疲労感が強まり、集中力が低下。高速道路を使った移動や、舗装の粗い路面では、その違和感がはっきり現れます。
また、タイヤの中央部が過度に摩耗する「センター摩耗」も起きやすくなり、均等な摩耗が得られないままタイヤの交換時期を迎えてしまうこともあります。快適性だけでなく経済性の面でもデメリットです。
タイヤ規格の違いに合わせた空気圧調整が必要
タイヤにはJATMA・ETRTO・TRAといった規格があり、それぞれ設計基準や空気圧の前提が異なります。安全に走行するには、規格ごとの違いを踏まえた空気圧の調整が不可欠です。
なぜ調整が必要なのか
タイヤの空気圧は、使用している規格によって基準値が大きく異なります。日本国内で一般的なJATMA規格のタイヤと、ヨーロッパのETRTO規格、アメリカのTRA規格では、同じサイズ表記であっても内部構造や対応する荷重性能が異なるのが特徴です。
例えば、205/55R16というサイズ表記のタイヤでも、JATMA規格とETRTO準拠のXLタイヤでは、適正な空気圧が異なることがあります。この違いを無視したまま使用すると、タイヤの本来の性能を発揮できず、走行時の安全性や乗り心地に影響が出てしまうでしょう。特に、輸入タイヤを使用する場合や、サイズ変更を伴う交換を行う際には注意が必要です。
タイヤの側面に記載されている表示だけでなく、どの規格に基づいた製品かを確認し、それに応じた空気圧へ調整することが求められます。
XL(エクストラロード)タイヤの場合
XLタイヤは、標準的なタイヤよりも高い負荷に耐えられるよう強化された構造になっています。そのため、基本的にはやや高めの空気圧での使用が前提です。純正装着タイヤがSTD(標準規格)である場合、同じサイズであってもXL規格へ交換するときは、空気圧の設定を見直さなければなりません。見た目のサイズが同じでも、内部構造の剛性が異なるため、STDと同じ空気圧では負荷能力が不足するおそれがあります。
空気圧の具体的な設定値については、タイヤメーカーが公表している負荷能力表や空気圧換算表を参照するのが一般的です。適切な空気圧を保たなければ、偏摩耗やバーストのリスクも高まるため、特に注意しましょう。
LT(ライトトラック)タイヤの場合
LTタイヤは、商用バンや荷物を多く積む車両に向けて設計されたタイヤです。高荷重に耐えるために空気圧も高めに設定されています。
一般的な乗用車用のタイヤと比べると、同じサイズであっても内部構造が異なり、空気圧は50kPa以上高めに設定されることも少なくありません。LTタイヤを乗用車に装着する場合でも、規格に合わせて空気圧を調整しなければ、本来の性能が発揮されません。
特に注意したいのは、車両側に指定されている空気圧がSTDタイヤ用のものである場合です。このとき、LTタイヤに置き換えるだけでは不十分で、負荷能力を担保できるだけの空気圧を再設定する必要があります。
なお、LT規格のタイヤは乗り心地や操作性に影響するため、乗用車に使用する際は整備士や販売店と相談のうえで適正な空気圧を見極めることが重要です。
エアゲージを活用しよう
タイヤの空気圧は目視だけでは分かりにくく、知らないうちに不足していることもあります。正確な数値を知るには、エアゲージの活用が欠かせません。
エアゲージを活用して定期点検を
タイヤの空気圧は、見た目や手触りでは判断しづらく、少しだけ低下している場合は気付かないこともあります。特に扁平率の低いタイヤは、空気が抜けていても外観に変化が出にくいため注意が必要です。
こうしたときに役立つのがエアゲージです。ホームセンターやカー用品店で手軽に購入でき、アナログ式やデジタル式など種類も豊富にあります。バルブに当てて数値を確認するだけの簡単な操作で、空気圧の管理がしやすくなります。
また、ガソリンスタンドに設置されている空気入れにもゲージ機能が付いていることが多く、セルフ式でも数値を見ながら補充できる仕様です。そのため、専用の機器がなくても、日常的な点検は十分に行えます。
測定のタイミングは「冷えている状態」で
空気圧を測るときは、タイヤが十分に冷えている状態で行うのが基本です。走行後のタイヤは中の空気が熱で膨張し、実際よりも高い数値が表示されやすくなります。正しい空気圧を確認するには、朝の出発前や、長時間車を停めていた後のタイミングが適しています。近くのガソリンスタンドまで数分走るだけでもタイヤは温まるため、できれば移動前に測るのが理想です。
逆に、炎天下や走行直後に測定すると、空気圧が高く表示されることがあります。この状態で空気を抜いてしまうと、本来より低すぎる空気圧になってしまうおそれがあります。測定のタイミングを間違えるだけでも、空気圧管理にずれが生じるため注意が必要です。
理想は「月に1回」点検
タイヤの空気は自然と少しずつ抜けていくもので、何も異常がなくても1か月に10〜20kPaほど下がることがあります。放置したまま走行を続けると、燃費の悪化やタイヤの偏摩耗、ブレーキ性能の低下といったリスクを引き起こす可能性があります。
こうした影響を未然に防ぐためにも、空気圧の点検は「月に1回」がひとつの目安です。走行距離が多い方や、高速道路を頻繁に使う場合は、さらに頻度を上げて点検してもよいでしょう。
定期的に点検することで、いつの間にか空気が抜けているといった事態を防ぎ、走行時の安心感を保ちやすくなります。慣れれば5分もかからない作業なので、給油や洗車と同じ感覚で習慣化するのが理想です。
空気圧を適切に管理して、安全で快適な走行を
タイヤの空気圧は、定期的に確認して管理することで、事故や余計な出費のリスクを減らせます。使用するタイヤに適した空気圧を維持することで、偏摩耗を防ぎ、タイヤの寿命も延ばせます。空気圧の設定に迷ったときは、整備士に相談することで、車両や使用状況に応じた調整が可能です。
浦和自動車解体では、不要になったタイヤの買取や中古タイヤの販売を行っています。倉庫に保管されたままの不要タイヤや、使用しなくなったスタッドレスタイヤなどの処分も可能です(※一部対象外あり)。交換用の中古タイヤを探している方には、予算を抑えた選択肢としてご案内しています。詳しくは以下よりお問い合わせください。
お見積もりはお気軽にお問い合わせください!
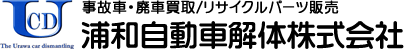
〒338-0824
埼玉県さいたま市桜区上大久保93
TEL 048-854-9923 / FAX 048-855-7848
R京浜東北線 北浦和駅西口より(埼玉大学行き)バス乗車約15分
JR埼京線 南与野駅西口より(埼玉大学行き)バス乗車約10分
「埼玉大学」バス停下車 徒歩約3分